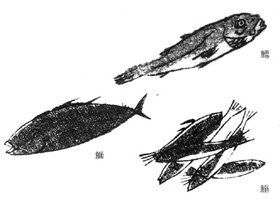pre top next
pre top next
pre top next
江戸の冬・師走の風物・食材
(今の暦では一月半ばから二月半ば頃)








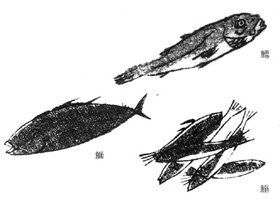
●節分の夜 大坂の市民五、六人が、或いは揃いの服を着て、或いは揃いでなくてもその中の一人が生海鼠なまこに細い縄を付け、地上を引いて歩く。その他の三、四人は「うごろもちは内にかとらごどんのおんまいじや」といいながら自分の家や知り合いの家に行って祝う事をする。「うごろもち」とは土龍もぐらのこと。江戸では「むぐろもち」という。大坂の人はこの夜だけいう。生海鼠を虎子殿と言い伝えて行なっている。これをすればその年、土龍つまりもぐらの害にあわないとする古い習慣。
●厄払い 京坂は節分の夜だけ来る。江戸も古くは節分だけだったが、文化元(一八○四)年以来、大三十日注1、正月六日、正月十四日にも来る。追儺ついなの豆は大坂では年数を数え、一銭をそえて白紙に包み、厄払いに渡す。江戸は十二銭をそえる。京坂の厄払いは「厄払いましょう」という。江戸は「御おん厄御厄」と御の字を付ける。厄払いの言葉はその節の付け方や文句は三都ともに似ているが、言葉は年々色々ある。その一例。
「ああらめでたいなめでたいな、だんな住吉御参詣、反り橋から西をながむれば、七福神の船遊ぴへ中にも戎という人は、命長柄ながえの竿を持ち、めぎすおぎすの糸を付け、金と銀との針をたれ、釣りたる鯛が姫小鯛、かほどめでたき折からに、いかなる悪魔きたるとも、この厄払いがひっとらえ、西の海とは思えども、ちくらが沖へさらリ云々」或いは役者名盡づくし、魚盡、何盡と色々いうう。
●節季侯 せっきぞろ。幕末には大坂にはないが、尾州以東にはまだある。江戸の節季侯は、紙の頭巾に紙の前垂れを着て、男女の乞食が混じりあってささらをすりながら太鼓を打ち、忙しい最中に来て囃し、銭をもらう。
●江戸年の市 門松、注連縄を始め、神棚や神具、その他色々な正月用品を売る。十二月十五日深川八幡、十七日浅草寺、十八日に同じ所で「簔市みのいち」というのがあるが同じこと。この両日を最も盛んとする。二十日神田明神、二十四日愛宕、二十五日麹町天神、二十六日から晦日まで、日本橋四日市その他の辻々でこれらを売る。
●寒中丑の日 『東都歳事記』を見ると、この日にみな鰻を食べるとしてある。しかも土用中、丑の日のあとには何の記述もない。ただし、この夏の土用の丑の日に鰻を食べたことは色々の説が残されているので、実際あったとみてよい。その例をいくつか出しておくと、天ぷらと一緒で、鰻屋が平賀源内に頼んで丑の日に鰻を食べれば夏にまけないとか、元気になるといわせたとか、それを宣伝に使ったとか、同じことを蜀山人しょくさんじん大田南畝なんぽがやったとか伝えられている。本山荻舟てきしゅう著『飲食事典』によれば、みずから丑の日元祖と名乗った神田和泉橋通りの春木屋善兵衛という人が、出入リ屋敷の藤堂和泉守家から、暑い時期に鰻の蒲焼の保存法をたずわられて、土用の子ねの日から、三日間にわたって焼いた鰻を瓶に入れ、密封して穴蔵に貯蔵したところ、丑の日に焼いた鰻だけが色も香りも、味わいも変わらなかったので、暑気の滋養になるとしたと書かれている。
こうして見てくると、ほかに比較するものがないので、寒中丑の日が正しいか、夏の土用丑の日が正しいかはわからない。しかし、荻舟氏も書かれているように、江戸時代には秋から冬へかけての利根川を下る鰻は利根川下りといって上品としたのをみてもわかる通リ、江戸っ子の上品な人たちは寒中丑の日に鰻を賞味したろうことは理解できそうだ。逆に、江戸時代の末期になると、今と同じように有名な鰻屋は、夏の土用の丑の日は店を閉じたという話もある。
●新酒 日は決められないとして、昔は九月に船が着いたが、近頃は次第に船の着くのが遅くなリ、正月頃から二月頃に着くと「東都歳事記」にある。船が着くと、たちまち酒問屋から迎えの大茶船注2を出して引き取リ、これを方々ヘ配るとしてある。その繁盛のさまは、例えようもない、とも。
●白魚しらうお 『東都歳事記」を見ると、ある書によると、江戸の白魚は古くは尾州名古屋の白魚を御取り寄せて任せられたという。またある説には、白魚の子を多く持ったものをたくさん捕ってそのままに乾かしてしまっておき、冬になってからこれを囲いの中に放しておくと子が自然と大きくなリ、白魚の形になった頃、囲いをとく。ここで生まれた白魚の子なので、よそにはいかずここにいると書き、これは荒唐無稽のようだが、読んだままをここに書いておくとある。
江戸の白魚は、十一月から春になるまで、毎夜佃沖で四つ手網注3を使ってとる。かがり火も多い。初春は海にいて、二月頃、川へのぼるとも書かれている。
注1 大三十日 大晦日のこと。
注2 大茶船 岸に近付けない大型の船の荷を岸に運ぶための船。
注3 四つ手網 四方に手のある網。
●十二月の魚と野菜 この項で引いた江戸の料理本には当月の「膾の部」が書かれていない。そこで他の本から魚類をさがしてみると鰡ぼら。藻魚、これは近梅の藻の中にいるめばるなどをまとめてこう呼ぶ。鮭、なまこ、鯛、鰹、さわら、丹後鰤などがあげられている。
「煮物の部」には塩鮎、一塩鯛、白魚、縮緬雑魚ちりめんざこなどが登場。塩鮎はせんば煮。せんば煮とは塩魚をもとに大根などを入れた塩味の煮物。魚と塩松茸の刻んだものと芹の根を煮て、輪切りの柚をそえるというのもある。一塩鯛は青昆布と煮て胡椒をそえる。白魚は青のりとしんじょ注4をかける。銀杏、大豆、柚のさいの目、玉子のふわふわというのもある。縮緬雑魚は海苔に。
「汁の部」を見ると、鯛のたたき、小鮒、つみいれが魚類。わかめの汁。ちょろぎ注5と芽独活注6。なめ茸と小蕪。鯛のたたきと菜を細かにして汁に、というのもある。なずな、大赤小豆の汁。子芋を面取りしてうこぎと汁に。うこぎというのは樹木で、この若葉を使う。紫蘇の穂と赤小豆の汁。小鮒を赤薄味噌汁に。若菜の汁。つまみ菜は赤味噌で汁。つみいれ玉子とちらし海苔の汁。
「猪口の部」には鮑、白魚、なまこが魚類として登場。蕪の猪口は山葵味噌和え。鮑ははららごと白酒をかけて。白魚は青和え。なまこは生姜酢。納豆類という猪口も出ている。百合根と梅ぴしお、砂糖を入れて和えるというのもある。糸切りこんにゃく芥子巻き。煮梅、砂糖かけてなど。
●冬、十月、十一月、十二月にわたる魚と野菜
「焼き物の部」としてはうるめ鰯。蒸し蒲鉾。塩鰤は酒煮。雉きじ付け焼き或いは油で揚げる。鮒はさがらめ巻き注7、枯れ松葉で止めて。酒の粕漬。蒸し鱈白酒、或いはあさじ酒とあるが、あさじ酒とは粳米うるちまいと糯もちごめ米を半々にして造る酒で土の中に入れて夏取り出すとされる。これは大分、熊本の名産。
「吸物の部」では梅干と海苔。鴨と巻き湯葉。鮑を薄く切り芹根。鮭と葉付き大根。いり鳥と紫蘇の穂。つくし。むき蜆と蕗の薹。田作と梅干、割り胡椒。すくい卵と蕗の薹。雁と芹根。塩松茸傘茸ともやし。鳥類と松露。大松露輪切り生海苔。
「取肴の部」では達磨味噌。これは青い九年母くねんぼをすりおろして酒で混ぜたもの。通常は添え物にする。九年母というのは蜜柑に近い柑橘類。色付慈姑。むき胡桃。すずめ焼。鮭のすじこ。鯖の麹漬。数の子辛子和え。鮑の田楽。蕗味噌。海鼠腸このわた。うるか注8。味噌煎り牡蠣。縮緬雑魚。
「重箱一重二重、引き物」は塩鱈、だし煮昆布、焙炉ほいろ注9にかけ。塩鰤白酒煮。牡蠣田楽山葵味噌。鰹味噌漬け、蒸して山葵の粉をかけて。大椎茸裏付。裏付には蒲鉾かはんぺんがよいとある。
注4 しんじょ 本来は鳥や魚の身をすりおろして山の芋と小麦粉を入れて蒸して固めたものをいうが、ここでは味をつけた山の芋のようだ。
注5 ちょろぎ 紫蘇の類の根で、古くは煮て茶請けにしたとあるが、現在は黒豆の中に紫蘇で漬けたものを入れる。
注6 芽独活 独活の早い時季の芽吹きの先のことをいう。
注7 さがらめ巻き 荒布に似た海苔で巻くことをいう。
注8 うるか 塩漬にした鮎のはらわた。
注9 焙炉 木の枠や籠を使って底に厚紙を張リ、下から炭火であぶる道具。
筑摩文庫『江戸あじわい図譜』高橋幹夫著 より
このシリーズもちょうど一年、今回で終わりです。